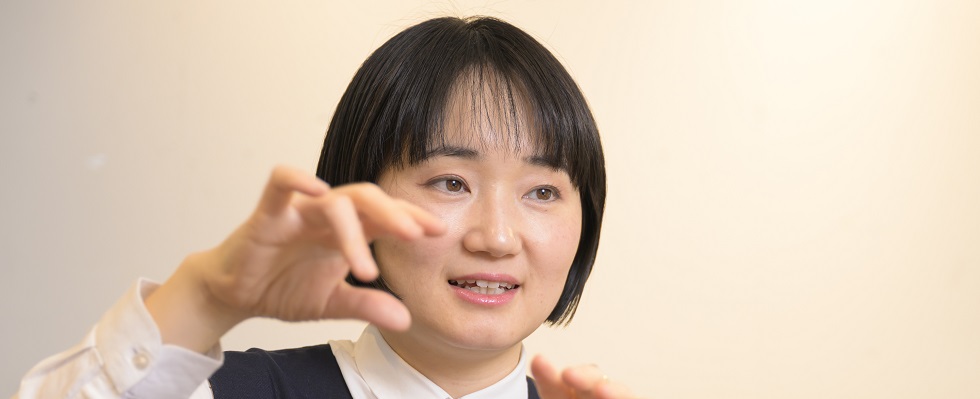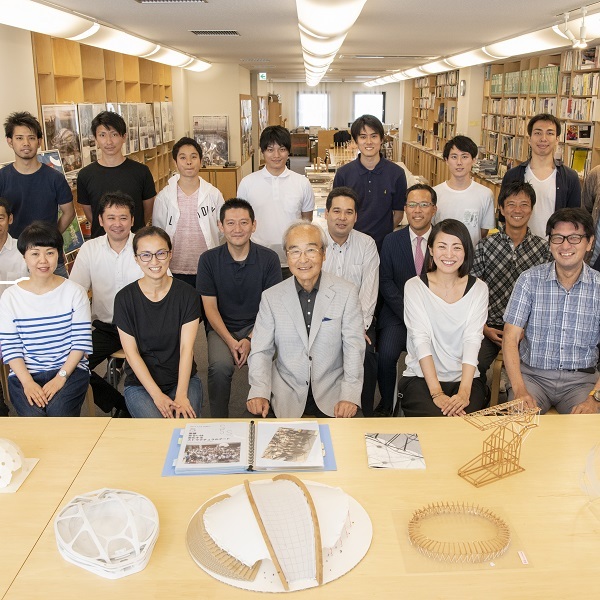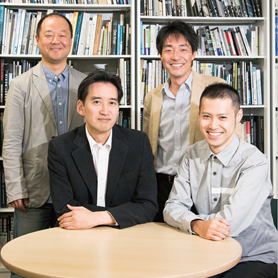私たちの職域はとても広い。 人々の思いと建築家一人ひとりの才が つながっていけば、いろんなまちが もっと豊かに、楽しくなると思う
大西麻貴
近年活躍する若手のなかでも、とりわけ注目されている建築家ユニット「大西麻貴+百田有希/o+h」。住宅やオフィスのほか、公共空間、福祉施設など幅広く手がけ、日本建築学会賞をはじめとする受賞作品も多い。主なものとして、「二重螺旋の家」「GoodJob! Center KASHIBA」「シェルターインクルーシブプレイス コパル」などが挙げられる。作品一つひとつの背景には、その場を利用する人々や地域特性、時間を一連のものとして捉える思想があり、それが豊かな建築を生み出している。大西らが一貫してテーマにしているのは「生き物のような建築」。建築と人間の関係を問い直す意味において、これは一つの重要な指針となっている。
一つひとつの仕事に丁寧に向き合い、学びを重ねていく
2008年、大学院を修了した年にo+hを開設。デビュー作「二重螺旋の家」は第28回新建築賞を受賞し、大西らは早くから〝期待される若手ユニット〞として注目を集めてきた。以降、公共建築や福祉施設を手がけるなど、その活動の幅を広げていく。
●
大学院を修了しても「千ケ滝の別荘」が継続中でしたし、追って「二重螺旋の家」の仕事も入ってきたタイミングでした。この頃には百田が伊東さんの事務所に入ることが決まっていたので、私が両方の仕事を引き継いだのがo+hの始まりです。共同主宰のことを伊東さんに相談したところ、「いいよ」と快諾してくださって。ただ、百田は伊東さんの仕事に全力投球するべきなので、伊東事務所に在籍している間は、休みの日などにo+hの仕事に参加してもらっていました。
5年ほど経って百田が戻ってきてから取り組んだのが「Good Job! CenterKASHIBA」。障害のある人とともに社会に新しい仕事をつくり出すことを目指す場です。この仕事を通じて、いつの間にか自分の世界の見方が180度変わっていたという点において、強印象に残るプロジェクトの一つとなりました。
最初の頃は、障害のある人が過ごす空間には、特別な配慮が必要だという気持ちがどこかであったのです。そのため、クライアントである「たんぽぽの家」の方に「何か気をつけることはありますか」と聞いたのですが、即座に「ありません」と。身体で感じる居心地の良さ、悪さは誰にとっても同じだから、特別なことをする必要はないというのです。また、障害のあるメン
バーが自分のアート作品を説明する場に立ち合った時のこと。その人がうまく説明できなかったりすると、周りに自然と笑いが起きる。本人たちも「ウケちゃった」とまんざらでもなさそうで、場自体がすごく寛容な雰囲気だったことに驚きました。誰もがありのまま、自然でいいという、当たり前のことに気づかせてくれたのです。
●
別の視点で学びが大きかったのは、〝チームでつくり上げていく〞素晴らしさだ。同プロジェクトではチームのつくり方も特徴的で、地域の人も含めた様々な立場の人たちが集められ、「どうつくりましょう?」からともにプランを育てていったという。地域や人々との対話を重んじる大西のスタイルが培われたのは、この時の経験が大きい。
●
メンバーとしては30人くらいだったでしょうか。町工場のおじさんとか大学の先生、あるいはクライアントと一緒に仕事をしている会社の社員さんとか、実に様々な立場の人たちが集められました。それも、あらかじめ役割が決まっていない会議体です。面白いもので、ほとんど無計画なところから始めると「自分ならこれができるかも」と自然発生的に役割が決まって、どん
どん活気づくのです。いい場ができていく、仲間が増えていくという感覚を味わいました。
アイデアがプロセスの途中で何度も大胆に変化していくのは、建築の醍醐味だと思います。Good Job! Centerがまさにそう。何度も足を運ぶうちに、皆で考えるうちにプランが変わっていき、最終案に至るまで2年ぐらいかかりました。でも、その変化の過程自体が、場の役割と可能性を皆で考える時間だったと思います。建築家の役割はどんどん変わってきているのではないでしょうか。あらかじめ決まっているプログラムにかたちを提示すればいいのではなく、場がどうあるべきか?をクライアントや利用者とともに考え、伴走していく。その価値、大切さを教えてくれた仕事でもあります。
その教えは、後にかかわった児童遊戯施設「シェルターインクルーシブプレイス コパル」にも生きています。これは山形市発注のPFI事業コンペだったのですが、建築だけでなく施工と15年間の運営をセットで提案するという点に魅力を感じ、チャレンジしたものです。こちらも「ともにつくる」体制で、設計の初期段階から建設、運ープが、段差解消の機能を持つだけで
なく、子供たちが駆けっこをする坂道にもなっているわけです。障害のある人をサポートするつくりが、ほかの人にとっても遊びや学びにつながるよう心がけたつもりです。インクルーシブな施設として多様な利用者が訪れていること、それが何より嬉しいですね。営、維持管理チームが一体となって計画が進められてきました。「すべての子供たちに開かれた遊び場のあり方」に
ついて議論を重ね、協働してきたからこそ、創造的な場ができたのだと思っています。
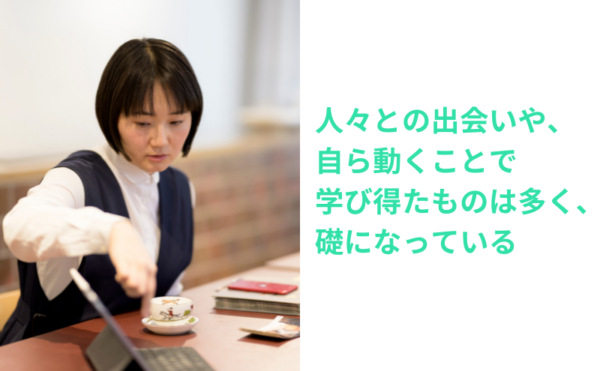
設計で大切にしたのは、一つのものに複数の意味を重ねていくデザインで、それがコパルの特徴にもなっている幅広のスロープ。体育館と大型遊戯場をスロープでつなぎ、建物全体を回遊できるようになっているのですが、スロープが、段差解消の機能を持つだけでなく、子供たちが駆けっこをする坂道にもなっているわけです。障害のある人をサポートするつくりが、ほかの人
にとっても遊びや学びにつながるよう心がけたつもりです。インクルーシブな施設として多様な利用者が訪れていること、それが何より嬉しいですね。
- 【次のページ】
- 建築を通じて理想郷を描く――その可能性を追い求めて

- 大西 麻貴
Maki Onishi 1983年5月13日 名古屋市名東区生まれ
2002年3月 南山高等学校女子部卒業
2006年3月 京都大学工学部建築学科卒業
2008年3月 東京大学大学院工学系研究科
建築学専攻修士課程修了
4月 大西麻貴+百田有希 /o+h共同主宰
2016年4月 京都大学非常勤講師
2017年4月 横浜国立大学大学院Y-GSA客員准教授
2022年4月 横浜国立大学大学院
Y-GSAプロフェッサーアーキテクト(教授)
家族構成=夫