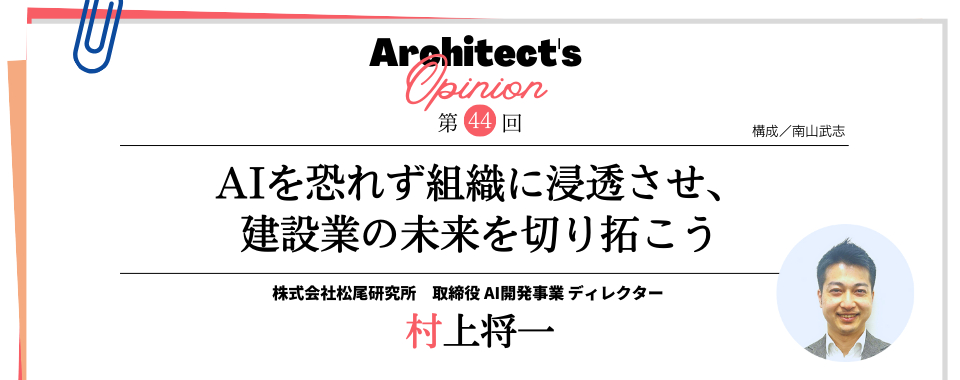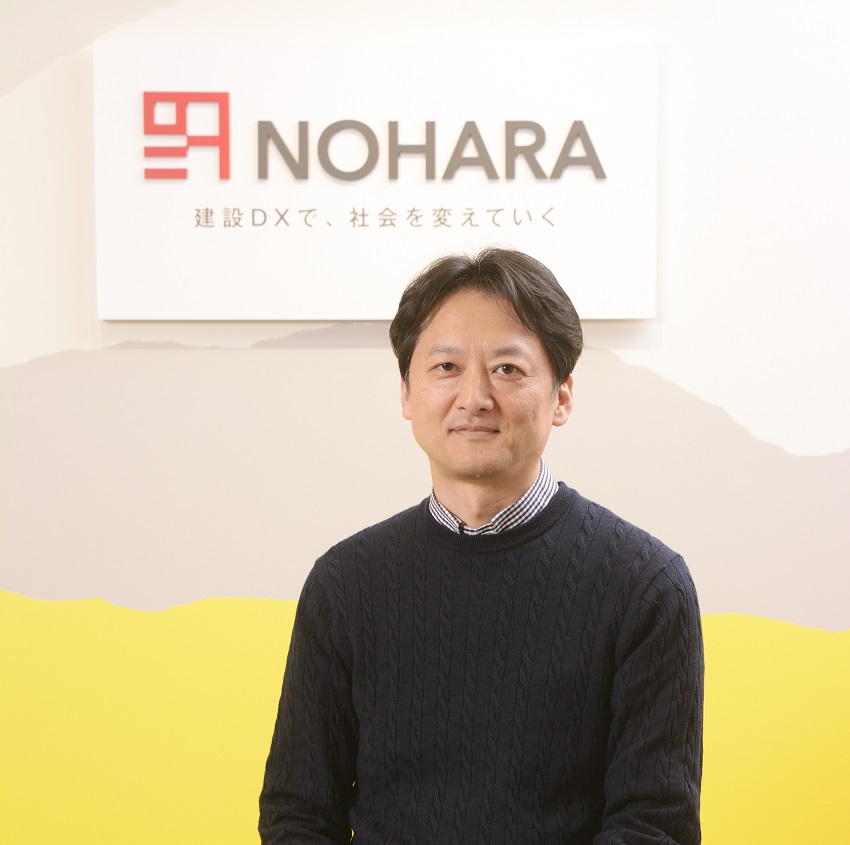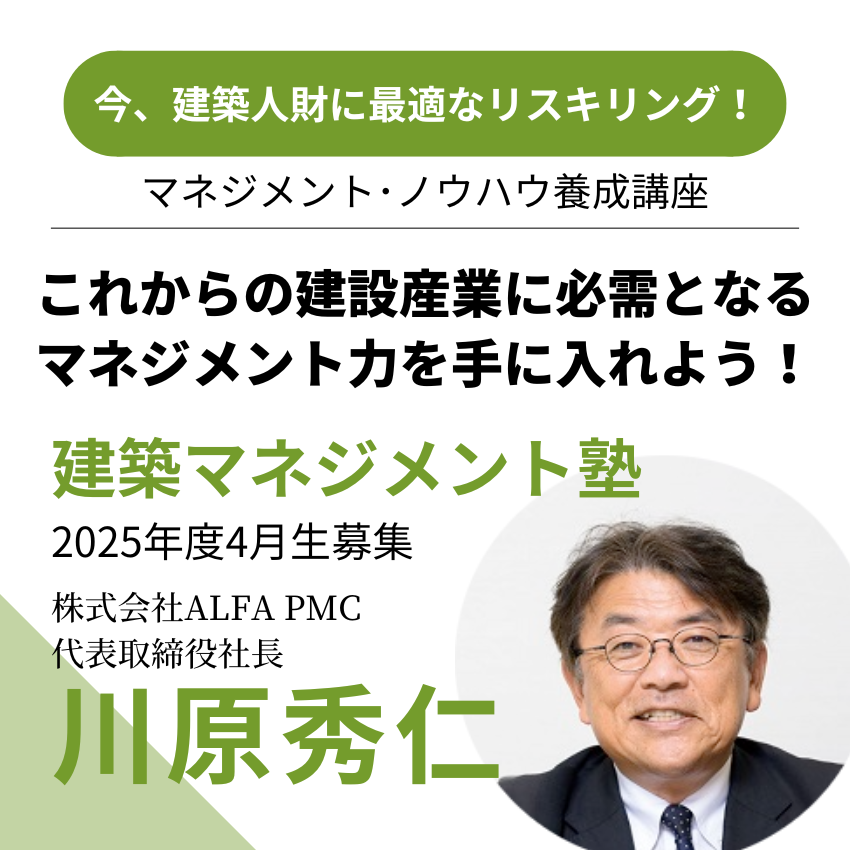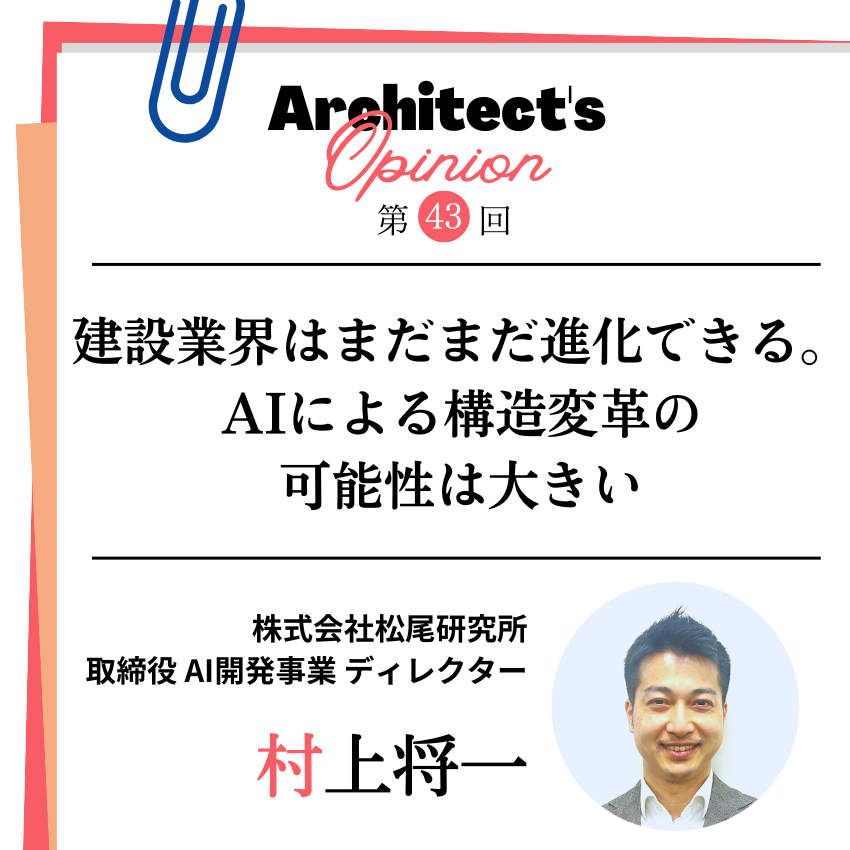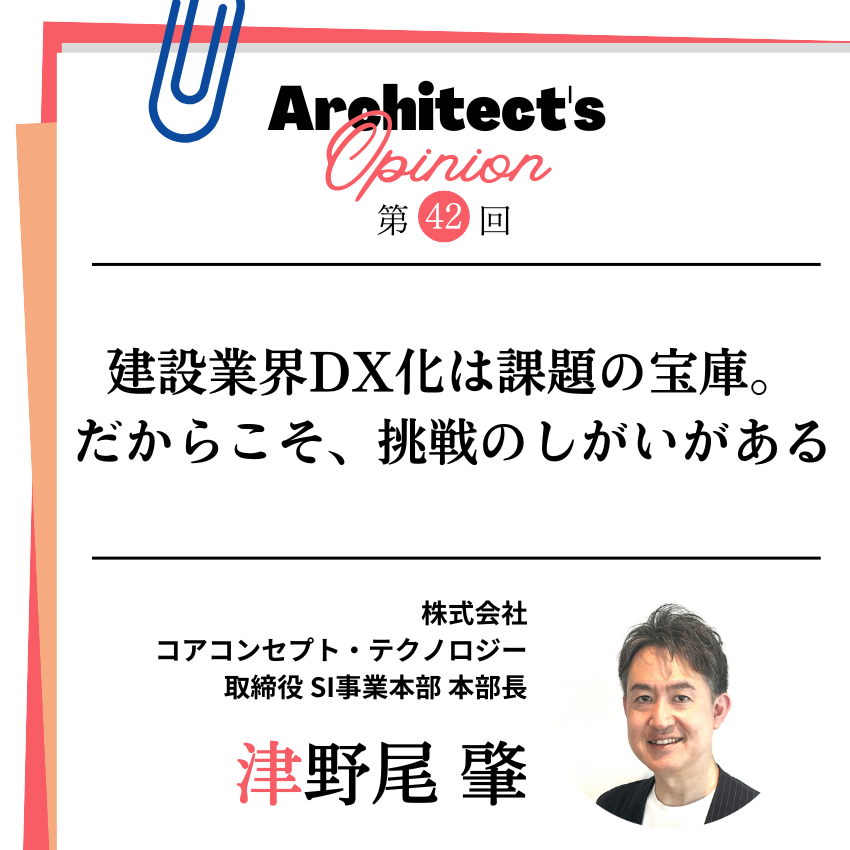AIを恐れず組織に浸透させ、 建設業の未来を切り拓こう
株式会社松尾研究所 取締役 AI開発事業 ディレクター
AIが導き出す回答は、あくまで推論であり、必ずしも100%の精度で正解が得られるわけではない。しかし、建設業界を含め、実際にAIを導入した企業の中には、その精度が完璧でないことに失望し、「まだ使えない」と早々に活用を断念するケースが少なくない。また、一定の精度が出るまでベンダーに過度な要求をする企業も見受けられる。こうしたAIの特性に対する理解不足が、AIの社会実装を阻む要因の一つになっている。
重要なのは、AIを「完全な正解を出すもの」と捉えるのではなく、「組織の生産性を向上させるサポートツール」として活用することだ。
例えば、建設業では法令順守が大前提となる。AIを活用してチェックを行う場合、出力結果をそのまま鵜呑みにするのではなく、人間の判断を適切に組み合わせることで、精度を高めながら業務効率を改善できる。その際、チェック基準を明確にし、判断材料となるデータをセットで提供することで、より実用的な運用が可能となる。
現状では、このような視点でAIを活用できている企業は限られている。しかし、AIを単なる実験的導入で終わらせず、組織全体に浸透させることで、その真価を発揮させることは可能だ。AIに関する正しい理解を深め、組織的な活用方法を模索することが、今後の競争力を高める鍵となる。
特に建設業界では、今、大きな変革のチャンスが訪れている。建設業界においても、生産性の向上が重要なテーマとなっており、現場の効率化が求められている。また、業界全体が生産性向上に向けた変革の必要性を強く認識している。そして、その変革を後押しする技術革新がまさに到来した。「生成AI」の登場である。
この技術は生産性向上に最適なツールであり、単なる試験導入で終わらせず、組織の業務プロセス全体に組み込んでいくことで、建設業の未来を大きく変える可能性を持っている。
もう一つ、建設業界に携わるようになって痛感した課題がある。それは、業務プロセスが細分化されているがゆえに、業種間で情報やデータが十分に共有されていないことだ。この分断を乗り越え、データ共有の文化を業界全体で醸成することも、AIを組織的に活用するために不可欠な要素である。
最後に、AIにかかわる者として、読者の皆様に伝えたいことがある。我々がクライアントにアンケートを取ると、いまだに「生成AIを使ったことがない」という人が多く、「AIに仕事を奪われるのではないか」という不安の声も根強い。
しかし、例えば「Google翻訳」を活用すれば、不慣れな英語で会話するよりも、より正確に意図を伝えられることが実感できるはずだ。こうした事実は、実際に使ってみなければわからない。AIは、単なる脅威ではなく、組織全体の生産性を向上させる強力なツールである。まずは、企業のリーダーや実務者が率先してAIの価値を理解し、組織全体で活用を進めることで、企業の未来を切り拓いてほしい。

- Shoichi Murakami
2008年、慶應義塾大学経済学部経済学科卒業。
大手損害保険会社、デロイトトーマツコンサルティング合同会社(Monitor Deloitte)を経て、
22年より現職。前職では、幅広い業種のクライアントに対してデジタル戦略立案や
新規事業構想のコンサルティング業務に従事。経営学修士。
東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻「松尾・岩澤研究室」学術専門職員も兼任。