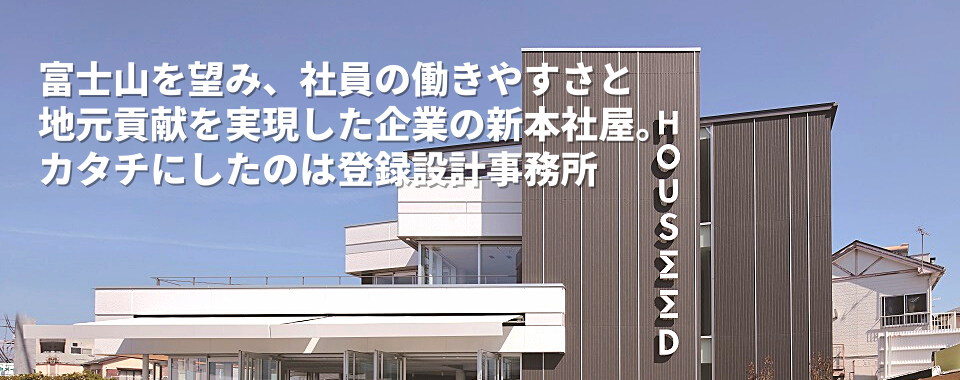【第17回】建築デザインへの不理解を払拭し、 必要な建物が実現しやすい社会に
東北大学大学院工学研究科 教授 建築史・建築評論家 五十嵐太郎
前回、今の日本には「目立つ建物はつくるな」という社会的な圧力のようなものが蔓延している、という話をした。その風潮は、東北の被災地復興の過程にも如実に顔を出していた。
例えば、ある大学でこんなことがあった。校舎が被災して、建て直さなくてはならない。最初に提起されたのは、“復旧”だから「以前の設計図をもとに、そのまま再建すればいい」という話である。だが、その校舎は建ててから40年あまりが経過していた。当時とは、教育内容から何から大きく変わっており、キャンパス計画と連動した新校舎の将来計画もあった。これを機にアップデートするというのが、誰がどう考えても合理的である。
結局、急いでコンペを実施することになり、著名な建築家の手によって、新校舎は設計された。斬新で機能的な建物の完成に、現場は大いに喜んだ。そして誕生したその校舎は、ある建築雑誌のキャンパス特集に掲載される話が進んでいた。
ところが、それに対して大学当局から「待った」がかかったのである。「こうしたものが堂々と外部に出ると、目立つから」というのが理由のようだった。要するに、「震災で“焼け太り”したような印象を与えるのはまずい」「批判が怖い」ということだろう。そうした経緯で、記事の掲載は見送られた。
そもそも建て直しに当たっては、文科省から下りる予算額が決められていた。その範囲内で設計されており、“復旧”なので面積を増やしたわけでもない。“復興”ではなく“復旧”の思想に則った、そうしたお達し自体どうかと思うが、新校舎はそのどちらの要件も満たしていたのである。とすれば、問題にされたのは、建物の“デザイン性”だったことは明らかだろう。
そこにあるのは、日本社会における建築デザインというものに対する著しい不理解、あえていえばリスペクトのなさである。デザインは、建物を無駄に華美に彩るためのものではない。与えられた予算の中で、いかにしてより優れた空間を設計するのかというのも、その大事な役割なのである。にもかかわらず、デザインを努力すると、褒められるどころか、あたかも“悪者”のような扱いを受けることになってしまった。
非常に気になるのは、「被災者は被災者らしくあれ」という、社会の“同調圧力”に対する恐れが蔓延していることだ。こうした状況は、東北の被災地全体を覆っていた。復興のために多くの建築家が現地入りしたが、「余計なことをするな」「変わったことをするな」といった締め付けや自粛の空気の中、苦戦を強いられた話を、私は聞いた。被災者にお似合いなのは、粗末に見える仮設や復旧の建築なのだろうか。不幸な震災を乗り越えて前に進むためには、これを契機に新しいまちづくりが必要なのではないか――。そう考えた人たちは少なくなかったはずだが、現場には見えない壁が存在していた。
とはいえ、こうした状況を一人“臆病な”現地の自治体などの責めに帰すのは、酷だろう。「被災地らしく」を当たり前だと考えるような空気感は、確かにこの国で強まっていると感じるのである。“叩かれない建築”が求められる風潮は、被災地だけではなく、東京の公共建築をめぐるメディアの反応にも共通しており、そんな今の日本を象徴しているのかもしれない。

- 五十嵐太郎
Taro Igarashi 1967年、パリ(仏)生まれ。
90年、東京大学工学部建築学科卒業。
92年、同大学院修士課程修了。博士(工学)。
中部大学工学部建築学科助教授を経て、現在、東北大学大学院教授。
あいちトリエンナーレ2013芸術監督、
第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッショナーを務める。
『現代日本建築家列伝』(河出書房新社)、
『日本建築入門』( ちくま新書)ほか著書多数。